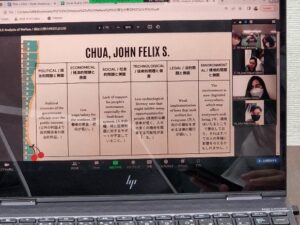ユネスコスクール支援内容
1.SDGs連携多角化プロジェクト「多様な視点でSDGs」 開催支援
大阪関西ユネスコスクールネットワークならびに大阪公立大学が開催機関となり、「ユネスコ未来共創プラットフォームの発展に資するユネスコスクールネットワーク活性化事業」の一環として、地域レベルにおけるユネスコスクール教員・児童生徒間の学びあい交流を行った。具体的に、企業、自治体、地域、など多様なステークホルダーによる異なる立場と世代を超えたESD/SDGsの実践共有などを通じてESD/SDGsの推進力の活性化を図る支援を行った。内容的には近畿・北陸地域のASPnet校の小・中・高・大学生が異なる学年、学校、地域、そして国を超えて行うネットワーク型ESD/SDGsの学びあい交流会(対面)を行い、継続的かつ直接的に児童生徒の「学びあい」と「協働実践」が可能となる広域ネットワークを発展・充実させることをした。プログラム構成は、多面的で多角的な活動やその成果に触れることでSDGsの各目標へのアプローチの広がりを共有する下記の3回シリーズで実施された。
◇第1回 ESDを学ぶワークショップ
◇第2回 ESDから考えるSDGsの世界
◇第3回 ESDで臨む学校・地域・世界のSDGs
(参加団体・学校は以下の通り)
アサンプション国際小学校、大阪府立佐野高等学校、大阪府立住吉高等学校、大阪府立松原高等学校、大阪府立長野高等学校、大阪府立淀川清流高等学校、大阪府立富田林中学高校、大阪府立城東工科高等学校、大阪教育大学附属高等学校池田校舎、大阪成蹊高等学校、帝塚山学院高等学校、奈良育英高等学校、奈良県立法隆寺国際高等学校、奈良県立国際高等学校、兵庫県立川西明峰高等学校、富山国際大学附属高等学校、神戸市立大沢中学校、箕面こどもの森学園、大阪公立大学、兵庫教育大学、関西大学、国際連合職員、滋賀県庁琵琶湖環境部、株式会社WAVE、京都嵐山「良彌」、羽曳野市職員ほか、

2.小学生による日韓オンライン交流(3回) 開催支援
兵庫県の山間地域にある姫路市立安富北小学校(ASPnet校)が韓国・清州小学校とオンライン交流を行った。両校のクラス児童がZoomを通して英語で相互に自己紹介をしあったり、地域や学校の特徴などを紹介しあったりした。想像の世界でしかなかった他の国の授業風景や子どもたちの「学び」が、現実の私たちのクラスと結ばれ、かつ「友」となった瞬間であった。この連携には大阪公立大学に在籍する韓国からの留学生が活躍し、日韓両言語を用いて交流の準備が円滑に進められた。(2022年度は年間3回の交流が実施された)

ESD活動紹介
1.大阪公立大学としての取り組み
大阪公立大学は、2022年4月1日に大阪府立大学と大阪市立大学が統合して開学した。統合後もSDGsが全学を挙げて取り組まれているが、とりわけASPnetを支援し、ESD/SDGsを積極的に推進しているのは、現代システム科学研究科/現代システム科学域である。特徴的なことは、環境学、言語文化学、人間科学、教育学、社会福祉学、臨床心理学、認知行動科学の各専門領域における教育研究を深化させるとともに、従来の学術領域の枠組みにとらわれない発想に基づく高度なシステム的思考力と領域横断的応用力を養い、持続可能な社会の実現に貢献する拠点となることをめざしていることである。国連教育科学文化機関(UNESCO)の ASPnet校にふさわしい総合的な支援がよりいっそう可能になるものと考えている。
2.日本・フィリピン学生によるESD/SDGsの共同カリキュラム開発
本学、大阪公立大学(OMU)現代システム科学域学生と、フィリピン教育大学(PNU)の学生が2022年11月~2023年1月にオンラインを通じてESD/SDGsの共同実践カリキュラム開発を行った。OMU側は約30名、PNU側は約60名が参加し、両国のSDGs推進上の課題と大きな問題点を相互に紹介し多視点・多角的・多面的にディスカッションを展開して、問題の共通性と異なる独自の事情とを理解しあった。最終的に、国際的に展開するESD/SDGsであることを前提に、国内のドメスティックな視点のみで考察することを逃れて自国の問題と他国との問題を同時に学ぶ学習展開案を作成することができた。これらは、ASPnet支援にも用いられる予定である。

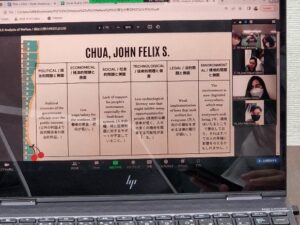
活動自己評価
https://www.unesco-school.mext.go.jp/supporters/aspunivnet/self-assessment/osakakouritsu/