| 所在地 | 〒560-0056 大阪府豊中市宮山町2-1-1 |
|---|---|
| 電話番号 | 06-6843-5288 |
| ホームページ | http://www.toyonaka-osa.ed.jp/cms/jh02/ |
| 加盟年 | 2012 |
2024年度活動報告
国際理解, 平和, 人権, 福祉, その他の関連分野


豊中市立第二中学校 2024年度活動報告
活動分野
国際理解, 平和, 人権, 福祉, その他の関連分野
本校は、持続可能な社会の作り手として、未来社会の形成に参画するための資質・能力を形成することを目指し、「違いを認め合い、すべての人が持続可能な社会を推進する生徒の育成」を目標とした。具体的には、①国際平和に係わる学習、②発達障害学習、③福祉体験学習、④地域と共に生きる学習を行いました。
① 国際理解・国際平和に係わる教育(全学年)
今年度も全学年対象に『戦火の子どもたちに学んだこと イスラエル、ウクライナ、アフガニスタンを取材して』という表題でフリーランスジャーナリスト、西谷 文和氏の講演を行いました。「戦争はなぜ起こるのか」「イスラエル、ウクライナで暮らす人々や子どもたちの現在の様子」「アフガニスタンで用水路をつくる活動をされていた中村哲さんいついて」、「中東の国の関連について」などの最新映像とお話をしていただきました。
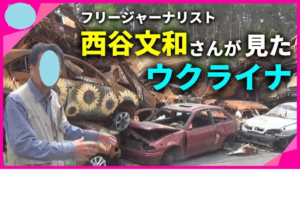
【生徒の感想】
・戦争をやめさせるために、戦争に賛成している人が「なぜ賛成しているのか」という理由を知ることで、対策や反対意見の伝え方を考えて、実施することができるんだと思った。急に捕まって裸にされて敵がいるのか、爆弾がまだ残っているのか、手を縛られた状態で確認させられることはとても怖いと思った。現代はインターネットが普及していることで、便利な世の中に見えるが、Tiktokやフェイクニュースでだまされる人が多いことを知った。だから、実際に起きた本当のことを知って行きたい。
・ウクライナ兵が戦地で足や腕を失いながらもリハビリをして、戦地に再び向かおうとする姿勢にただ母国のために動こうとしているのか、戦争というものに狂わされて正常な判断ができなくなっているのか分からず、複雑な気持ちになった。
・戦争をすることが自分たちに関係のないものだと思っていたけど、戦争をすることで地球温暖化が進んでいることを初めて聞いて、すごくびっくりした。当事者だけでなく、世界中の人たちが総力を挙げて止めなければならないことだと思った。中村哲さんのように、戦争を止められるように努力する人、止めることができる人がもっと増えるためにも、世界中の地域でジャーナリストの方の活動を広めていくべきだと思った。
・日本国憲法第9条が改めてすばらしいものだと感じた。他にも平和主義という考え方を持つ国があってほしいと思った。戦争や紛争の様子が日本に伝えられているけど、逆に日本の平和な様子を、戦争をしている国に伝えられたら、その国の人も考え方を改めるかもしれないと思う。
*他の取り組み
2年生では豊中市の国際交流センターの協力を得て、中国・韓国・インドネシア・タイベトナムの方に講師でお越しいただき、それぞれの国の文化や生活を教えていただきました。3年生は沖縄修学旅行で平和祈念公園やアブチラガマ、道の駅嘉手納を訪問し平和学習のまとめをしました。2年生は修学旅行に向けて事前として、学習ワークシートを使って「琉球・沖縄の歴史」を学び、「沖縄戦」の特徴を表すキーワードを提示し、調べ学習を行っています。


② 発達障害・人権に係わる学習(1年生)
本校はインクルーシブ教育を推進していますので、各クラスには様々な個性の生徒がいます。様々な個性を持った生徒たちが生活するクラスを考えるために、今回は「発達障がいってなんだろう」という一つのテーマで、NPO法人サンフェイスを講師として招き、発達障がいの特性について考えました。そして、様々な個性のある人と一緒に過ごすうえで大切にしたいことを学びました。グループワークを通して、より良いコミュニケーションの方法「視覚的・具体的・肯定的」について学び、全ての人にとって過ごしやすい環境をつくるにはどうすれば良いか考えました。発達障害について理解し、発達障害はグラデーションのように区切りがなく、お互いに「視覚的・具体的・肯定的」にコミュニケーションを取り、助け合うことで良い環境を作り出すことができ、それを自分なりにやっていきたいと多くの生徒が考えることができました。しかし、日々のクラスの人間関係のもつれの中で「やってもらって当たり前と思っている」と相手に対して否定的にとらえている生徒の考えも少数ながら存在します。今回学んだ考え方を、今後時間をかけながら、お互いの理解にむけてクラスづくり、学年集団づくりに活かしていきたいと考えています。また将来、卒業後も生徒たちには様々な個性の人がいる地域に根差して生活し活動をします。このように地域住民が共に生きやすいような心の土壌を育てることこそが、本校ができる地域のESDの一つであると考えます。
③ 福祉体験学習・人権に係わる学習(1年生)
「福祉体験学習」を行いました。豊中市地域共生課、障害福祉センターひまわりなどのボランティアの方々に来校していただき、白杖や車いすなどを体験し学習しました。
【生徒の感想】
◆車いす体験
・溝に落ちそうで怖かった。これで生活している方は大変だと思った。
・レバーをしないと坂の時、落ちそうになるのが怖かった。段差のところが車いすを上げないといけなくて難しかったです。
・乗った感想は、すごく緊張感もあったけど押してくれる人が丁寧で、降りるときに声をかけてくれたおかげで安心して乗ることができました。押した感想は、声掛けをしっかりしようと心掛けたのが良かったと思う。車いすを持ち上げるのは難しかった。
◆白杖体験
・階段で手引きがいたからスムーズに上がれたけれど、誰もいなかったら不安になると思う。毎日が見えずに生活しているのは大変だと思った。
・階段がとても怖かった。横に解除してくれる人がいるのがとても安心できた。
・少しの坂でも不安になった。人が多いと声が大きく聞こえて、周りに何があるのかわからなくなった。
・白杖があるなら別にサポートをしてくれる人がいなくてもよいのではないかと思っていました。その後、体験で実際にアイマスクをして白杖を持って歩いてみると、信じられないくらい怖かったのです。ただのまっすぐな道を、白杖とサポートしてくれる人で通るだけなのにとても怖かったです。


④ 地域と共に(竹林の保全、地域のつながり)
今年度も12月に地域の竹林に行き、PTA・地域の方々や阪大の竹林を守る会の方々と、門松に使用する竹を切り出しました。全校朝礼で生徒たちに竹林の存在と門松づくりの様子を知らせるとともに、大切に守っていく心を育成することができました。本校の門松には特色があり,「笑い竹」と呼ばれる節近くを切り取ることによって門松が笑っているように見えるものです。1月には、3年生の入試祈願と1・2年生の幸せを願って餅つき大会を実施しています。また、校区の連携としては、11月は地域スポーツフェスティバルを行い、保育園・幼稚園・こども園・小学校・中学校・地域スポーツ団体が集まりスポーツを通して地域のつながりを深める行事をしています。



来年度の活動計画
【来年度の活動計画】
来年度の今年度と同様に「多文化共生~国際社会を生きる人材の育成~」を活動テーマとして、SDGsの実践を通して、持続可能な社会の担い手を育て、多様な価値が存在する国際社会を豊かに生きる力の育成を目標とします。
具体的には、①国際理解に係わる活動 ②国際平和学習 ③人権に係わる学習 ④地域共同を中心に学習・体験・活動をします。
① 国際理解にかかわる活動
次年度は、外国の中学生との来校していただいての交流やオンライン等を利用した交流を再開していきたい。また、今年度と同様に、豊中国際交流センターとタイアップして講師を依頼する予定です。さらに、豊中市の姉妹都市であるサンマティオとも交流をしていきたい。さらに、阪大の国際交流センターが校区にあるので、日常生活においても多文化共生について考える機会が多い地域なので日常的な交流を目指していきたいと考えています。
② 国際平和にかかわる教育
現代の国際社会において、平和を維持するためにはどうすればよいか、生徒たちに考えさせる機会を与える。そのために、今年度と同様に外部から講師を招き、体験談をもとにした講演会を企画している。する。その前段階として各学年で平和に関する調べ学習(修学旅行で行く沖縄戦について)を行予定にしています。
③ 人権にかかわる学習
コロナ以降「人と人のつながりの大切さ」を感じています。可能であれば、ボランティア体験学習、職場体験学習を実施する予定です。人権について考える講演会を持ち人権を考える機会を持つ。インクルーシブ教育を推進し、様々な個性のある人々と共に持続可能な社会の担い手を育て体と考えています。
④ 地域共同
地域と共に生きる生徒の育成、地域の環境を考え保存していく生徒の育成を目指したいと思っています。

