
| 所在地 | 〒911-0843 福井県勝山市鹿谷町本郷34-1 |
|---|---|
| 電話番号 | 0779-89-2539 |
| ホームページ | http://sikatani11105.mitelog.jp/blog/ |
| 加盟年 | 2014 |
2024年度活動報告
生物多様性, エネルギー, 環境, 文化多様性, 世界遺産・無形文化遺産・地域の文化財等, 国際理解, 福祉, 持続可能な生産と消費, ジオパーク
本校は「豊かな心をもち、進んで学ぶ、健康でたくましい児童の育成」を教育目標に掲げ、ユネスコスクールの重点分野「持続可能な開発および持続可能なライフスタイル」について考える力の育成を目指した。その重点分野の達成に向けて4つの柱(環境・持続可能な生産と消費・福祉・持続可能なまちづくり)の実践を通して児童が自分たちの住む地域に対して主体的に考え、行動できる力をつけるための活動を行った。
(1)環境に関する取組
①セイタカアワダチソウ駆除活動
10/9(水)、6年生(9名)は勝山北部中学校2年生(12名)と校区内で繁茂しているセイタカアワダチソウの駆除を行った。長年にわたる活動で繁茂している場所や量が減少してきているが、身近な自然環境が破壊されていることを再認識し、地域の自然環境について改めて考えることができた。
②総合的な学習
5年生は、年間を通して鹿谷で多く見られるホタルについて調べた。外部講師を招き、町内を流れる鹿谷川で行った水生生物調査では、ホタルの幼虫が成長できる環境を調べ、わかったことを学習発表会で発表し、ホタルの生育にとって地域の環境が大切であることを町民へ発信した。ふるさとの川で多く見られるホタルについて学習したことで、地域の環境について関心を高めると同時に、自然と共生して生活していくことの大切さを考えることができた。
(2)持続可能な生産と消費に関する取組
①米作り(5・6年生23名)
今年度からバケツを用いた米作りに取り組んだ。5年生が7/12(金)に、6年生が16(火)に行った。9月下旬に刈り取り、2週間天日干しの後、脱穀した。その後、籾の選別の前後の数を比較することで、不良米が多くあることに気づき、自分たちが食べているお米には、生産者の労力が大きく関わっていることを認識し、食の大切さを考えることができた。
②さつまいも栽培(1・2年生23名)
4~6月に行った。10月に収穫し、乾燥させた後、スイートポテトを作り、食した。生活科での栽培体験を通し、児童は普段何気なく食べている食材が口に入るまでに多くの手間と時間がかかっていたことを知り、地産地消の良さと安全な食材について考えることができた。
③ラディッシュ栽培(3年生6名)
5~7月、理科の授業で観察した種を露地に撒き、収穫するまで間引きや虫取りを行った。無農薬栽培をしているため、虫に対して抵抗がある児童も見られたが、虫がつく=安全な作物であることを認識してからは、抵抗感なく作業に取り組んでいた。
(3)福祉に関する取組(3・4年生)
福祉学習(3・4年生14名)
11月、福祉についての関心を高めるため、福祉や介護、ユニバーサルデザインについて調べ学習を行い、学級内で発表した(複式学級のため、次年度1学期までの学習)。発表後、わかったことをまとめていく中で、福祉が特別なものではなく、人権を尊重した考えであることに気づくことができた。
今後、勝山市の社会福祉協議会の方を招き、シニア体験を通してお年寄りが1人で行動することの大変さを考え、お年寄への
サポートの仕方を学ぶ。また、お年寄りとの交流会を企画し、お年寄りのサポートを行いながらニュースポーツ大会を開催する予定。
(4)持続可能なまちづくりに関する取組(5・6年生)
①恐竜ひょうたんの栽培と置物作り(5年生14名)
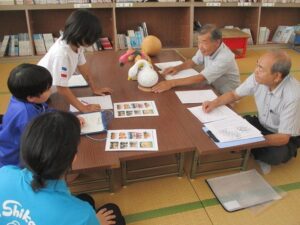
鹿谷町特産の恐竜ひょうたんについて、栽培に取り組んでいる方を招き、特産品になるまでの背景を学んだ。5~9月、まちまちづくり協議会および地域の関連団体の協力を得て、学校の畑で恐竜ひょうたんを栽培した。9月に収穫し、ひょうたんの下処理などを行い、10月に恐竜ひょうたんの置物作りを行った。作品は校内発表会や地区のまちづくり会館に展示した。地域の方から地域特産の恐竜ひょうたんの栽培の背景と置物作りの指導を受けることで地域の方との交流を深め、恐竜ひょうたんが育つ鹿谷の地に愛着をもつことができた。
②勝山の魅力再発見「勝山市や鹿谷をPRしよう」(6年生9名)
1学期、鹿谷町の魅力について考えるため、地域の方を招いて鹿谷町の歴史・文化・特産品について学び、PRするためのテーマを話し合った。2学期、自然・歴史・食べ物のグループに分かれて素材集めをし、ふるさと鹿谷町をPRする動画を作成した。作成したCMは、学習発表会で、児童や町民に向けて地域の魅力を発表した。CM作成を通して地域の魅力を改めて考えたことで、地域に対する愛着を深めることができた。作成したCMは、賛同が得られた地域の企業と連携し、期間限定で発信する予定である。
来年度の活動計画
来年度も引き続きESDをスクールプランに位置づけ、保護者や地域の方、関係機関の協力を得て4本柱(環境、持続可能な生産と消費、福祉、持続可能なまちづくり)を中心とした学習活動を各学年で行う予定である。環境は5年生の総合的な学習、持続可能な生産と消費は1・2年生の生活科を中心に、福祉は4年生の総合的な学習、持続可能なまちづくりは3~6年生の総合的な学習を中心に学習活動に取り組む。また、5・6年生の社会や理科の学習においては、地球温暖化による気候変動と災害の関わりや環境と人々のくらしとの関わりについて体験を通した学習を取り入れていきたい。
各学年の活動については11月の学習発表会で活動内容や成果を発表し合い、地域の良さや魅力を全校で共有し、下級生は次年度の活動の見通しをもつ場として設定する。併せて児童が自主的に取り組む態度を育み、次年度の活動の目標をもたせ、自ら体験することによって新たな発見があるように仕組んでいきたい。
