- おうびりんちゅうがっこうこうとうがっこう
-
桜美林中学校・高等学校
- J.F.Oberlin Junior and Senior High School
- 種別中等教育学校または中高一貫校等 地区関東地区
- 主な活動分野登録なし
| 所在地 | 〒194-0294 東京都町田市常磐町3758 |
|---|---|
| 電話番号 | 042-797-2668 |
| ホームページ | https://www.obirin.ed.jp/ |
| 加盟年 | 2017 |
2024年度活動報告
減災・防災, 環境, 文化多様性, 国際理解, 平和, 人権, 食育
2024年度は、高校3年生の学年がいわゆる「新課程」ということもあり、従来から準備してきた「探究・総合プログラムの中高6年実施」「新しい評価方法の導入」「DXハイスクールの採択」を掲げて教育活動を進めることができた。ユネスコスクール加盟8年目の今年は、それらの観点から可能な分野での活動を少しずつ広げながら、本校のユネスコスクールプログラムである、①平和学習プロジェクト②環境教育プロジェクト③国際理解プロジェクトと連携・発展させて、これまで以上に生徒たちに持続可能な社会の担い手に必要な知識、能力、態度、価値観を身に付けさせる学習を展開した。
①平和学習プロジェクト
本校はキリスト教主義を建学の精神に掲げているため、まず「心の平和」を達成することを目標として、聖書や礼拝の時間を使い、一年をかけてすべての生徒がノートを作成した。毎週の講話を聴きながら、生徒たちは平和な世の中をイメージして、自分の考察をその都度ノートにまとめている。そして、全教員がそのノートにコメントを書き、相互の評価を取り入れている。
入学式から5日目、中学新入生は町田から御殿場に場所を移し、1泊2日の研修を行っています。研修の目的は①桜美林学園の建学の精神を学び、「桜美林中学校」での生活を有意義なものとする。②初めて出会った友達との親睦をはかると共に、団体生活を通じて協力し、隣人愛、奉仕の精神を学ぶことです。長時間に渡る研修の時間でしたが、しっかりと自覚をもって取り組む姿勢が感じられ、よい研修の時となりました。

東京都のプロテスタント学校の生徒教職員が集まり「第15回東京-祈りの輪」が5月25日(土)に開催されました。桜美林からも生徒と教員が参加しました。今回は金沢にあるキリスト教学校の北陸学院高校の生徒2名と先生をお招きして、被災の状況や現状、また北陸学院が行っている支援活動についてのお話を聞きました。その後に小グループごとに分かち合いと能登半島地震を覚えて祈る時間を持ちました。キリスト教学校の生徒教職員が被災された方を覚えて祈る活動は15回目を迎えました。祈りから新たな行動と交わりの輪が広がっていくことを期待したいと思います。
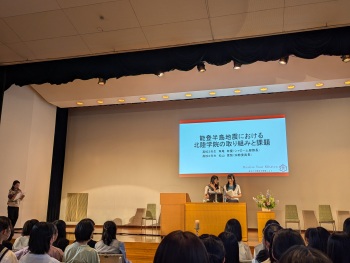
6月12日(水)中学校では花の日礼拝を行いました。1856年、アメリカのメソジスト教会で「こどもの日」として始まった花の日礼拝は、日本でも多くのキリスト教会やキリスト教学校で毎年6月に行われています。奉仕委員がお花の持ち寄りを呼び掛け、今年も色とりどりのお花に満たされたチャペルで恵みに満ちた豊かな礼拝が行われました。昼休みには委員の生徒の他、大勢のお手伝いの有志生徒たちが参加して、ラッピング作業を進めました。放課後、たくさん出来上がった花束を携えて、奉仕委員の生徒たちは周辺の各施設、幼稚園、学園本部や日頃お世話になっている方々などに訪問し、日々の感謝と共にお花をお渡してきました。

高校2年生は、「戦争と平和を考える」ために沖縄への修学旅行へ向かいました。1班は7月1日(月)から、2班は7月2日(火)から沖縄において、前半は「平和」についてしっかり学び、後半は沖縄の自然のなかでしっかり楽しむ4泊5日を過ごします。今も世界に目を向けると、戦火の中で尊いいのちが失われていく毎日です。オビリンナーとして私たちひとりひとりに何ができるのか、しっかりと考える旅にしたいと思います。

修学旅行から帰ってから、高校2年生は「沖縄平和記念礼拝」を行いました。礼拝の中で生徒が「沖縄修学旅行を通じて考えた平和」と題した作文を読み上げました。沖縄で見たこと、調べたこと、体験したことを元にそれぞれの視点から平和について考えが伝えらた。同級生が語る一つ一つの言葉を、礼拝に参加した生徒たちはしっかりと受け止め、また、平和合唱として「さとうきび畑」を全員で斉唱し、チャペルいっぱいに平和の歌声が響きわたりました。礼拝を通じて改めて平和の尊さと平和を創りだしていくことの大切さを心に刻むことができました。

12月30日(月)と31日(火)の二日間にわたって、横浜寿地区で行われた越冬炊き出し活動に生徒と教員の有志が参加しました。
桜美林中高では寿地区で活動する「神奈川教区寿地区センター」と連携して献金や献米などの支援を続けています。両日ともに朝から野菜や肉の切り込み作業を行いました。午後からは配膳作業を行い500人近い方が食べに来られました。また、スタッフの近藤さんの案内で寿の街歩きを行いこの地域の歴史や課題などを共有しました。生徒たちは多くのボランティアと協力して仕事をこなし、皆さんにあたたかい食事(30日は雑炊・31日は年越しそば)を召し上がっていただくことができました。寿地区は日雇い労働の街として発展してきましたが、近年は不況や高齢化によって町の様子も大きく変化しています。日本のさまざまな課題の縮図ともいえる場所で、生徒たちはまっすぐに現実を受け止めながら、よりよい社会の実現には何が必要か考える機会にもなりました。

②環境教育プロジェクト
中学1年生は
・自然の雄大さ、美しさ、厳しさに触れ、自然の大切さを知る。
・団体生活を通して思いやりの心を養い、協力することの大切さを知る。
・学年全体での行動を通じて時間を守ることの大切さや、ルール・マナーを守ることの大切さ=集団行動を円滑にすることを学ぶ。
を目標に掲げ、2泊3日長野県車山高原で行われました。到着後の1日目は、白樺湖や車山地域の自然や環境を学ぶ講座や観察などの学習プログラムが行われ、2日目は車山登山で、みんなで元気に登ってきました。

中学2年生は
・初めて出会う方々との生活を通し、「円滑なコミュニケーション」について考える。
・農業を通じて、自然の「恵み」や食の大切さを知る。そして自然と共に生きるすばらしさを感じ、自然を守り育てることが人間の役割であることを知る。を目標に掲げ、2泊3日で長野県飯田市方面でサマースクールを実施しました。農家のお宅での民泊を経験します。農家で1泊を過ごし、2日目の昼前にお世話になった家の方々とのお別れ式をしました。午後はクラスごと、SDGs体験と野菜の収穫体験を行いました。

4月18日(木)、19日(金)の2日間、2023年度さくらプロジェクト(3月23日~25日)現地活動報告を高校礼拝後に行いました。 3月23日(土)~25(月)の2泊3日の日程で、さくらプロジェクトは現地活動を行いました。初日は昨年同様、多賀城高校を訪問、多高生との交流会、災害マップを見ながら街歩きを行いました。多高の生徒会のみなさんによる丁寧なアテンドにより、13年前の東日本大震災の恐ろしさや、災害時に自分は何をすべきかなど、改めて多くのことを考えさせられるひとときとなりました。1日目の最後は今年も日本基督教団名取教会を訪問しました。
教会では荒井偉作牧師、防災士太田幸男さんから2011年3月11日14時46分に起こったこと、そしてその後のこと等を詳しくお聞きすることができました。2日目は7時前に宿を出発。閖上の日和山周辺を散策したのち、閖上朝市に向かいました。朝市では、清掃活動、店舗のお手伝い、競りのお手伝いなど、それぞれが持ち場に分かれて様々な経験をさせていただきました。身体を動かして労働を行った後、ゆりあげ港朝市協同組合櫻井広行理事長から講和をいただき、その後、各自漁港直送の海鮮丼や名取名物のセリ鍋などの名物で昼食時を堪能しました。午後には石巻市震災遺構大川小学校を訪ねました。震災の語り部活動を続ける只野英昭さんから丁寧な説明を受けながら、じっくりと大川小学校の遺構を見て回りました。今年はお天気が良かったこともあり、小学校の裏山の中腹まで登ることができ、ひとりひとりが震災当時の様子をそれぞれ頭の中にめぐらせながら、お話を聞き続けました。 3日目はリアス式海岸の美しい海岸線、牡鹿半島の民宿では豊富な海産物を使った朝食を堪能しました。朝食に出た「めかぶ」はちょうど今が最盛期です。朝食後の散歩では海岸での収穫の様子を見せていただきました。出発後は奥松島の素晴らしい海景色を遊覧船から見物、船長の巧みな話術に楽しみながらも、改めて自然の力の強さや脅威を感じる時間を味わいました。奥松島から東松島市震災復興伝承館を訪れました。ここは被災したJR仙石線の旧野蒜駅を活用し、伝承館として展示されているものです。 この旅で訪れたほとんどすべての場所は、10メートルを超える津波に襲われ、街が根こそぎ失われてしまったところです。そして、震災から13年経つ今も、その場所には人が住む家はなく、元のような街並みはありません。旧野蒜駅周辺も同様です。伝承館でも当時から今に至るまでの話を聞き、多くのことを考えさせられました。仙台へ向かい、建築家伊東豊雄氏によって設計された「せんだいメディアテーク」を訪れました。多くのことを考え、感じ、学び、思い、吸収する非常に濃い3日間を過ごしました。「わたしたちはどう生きるのか」あらためてその課題を与えられたように思います。

③国際理解プロジェクト
外国語教育と異文化理解教育を大切にしている本校では、年に一度すべてのプログラムを英語で行う礼拝(ENGLISH CHAPEL)を大切にしています。今年度は11月13日(水)から英語礼拝週間として、中高それぞれの学年礼拝が英語で行われました。中学校礼拝では、青山学院大学理工学部教授・学院宣教師のDavid W. Reedy先生から「THE GREATEST GIFT」(最高の贈り物)というタイトルでメッセージをいただきました。また、高校のEnglish Chapelは礼拝動画の放送という形で14日から各学年で行われています。高校では「TRUTH THAT SETS US FREE」というタイトルでAtouii Miyajima先生から奨励をしていただきました。

中学3年生は、①異文化を体験し理解する ②習得した語学知識を用いてコミュニケーションを図る ③国際公衆道徳を習得する ④他国を通して自国の文化や生活を見つめ直すことを目的として、オーストラリア研修旅行を実施しました。ホストファミリーにも温かく迎え入れていただき、生徒たちは普段経験できない貴重な体験を楽しみました。
卵の収穫をしたり、鶏や馬の世話をしたり、ホストファミリーと一緒に昼食を作ったりと、新たな発見に満ちた時間を過ごしています。また、午後には「ハンギング・ロック」という観光地で岩登りに挑戦した生徒もおり、暖かな日差しの中で自然を満喫しました。さらに、野生のコアラと出会うという感動的な瞬間を経験した生徒もいました。
ホストとのお別れ式の後、生徒たちはバスでメルボルンに向かい、各班に分かれて自主班行動を行いました。メルボルン州立図書館やフリンダースストリート駅など、趣と歴史を感じさせる建物を見学したり、お土産を買い回ったりと、思い思いに充実した時間を過ごしました。
夕食後には、予定を少し早めて解散式を行い、ファームでの体験を発表し合いました。久々の対面で自分たちの体験を共有し、思い出話に花を咲かせながら楽しいひとときを過ごしました。最終日、生徒たちはメルボルン博物館を訪れました。博物館の横では2クラス合同の集合写真を撮影し、さらに世界遺産に登録されている王立展示館の前でも各クラスで記念写真を撮りました。博物館内では、アボリジニの歴史やトリケラトプスの展示など、日本ではなかなか目にすることができない貴重な展示物に興味津々の様子でした。オーストラリアの文化と歴史に触れる、特別な時間となりました。

9月16日(月・祝)オーストラリアの姉妹校Emmanuel College Warrnamboolから、生徒たちが来校しました。昼過ぎに学校に到着し、桜空祭の2日目を桜美林のバディと共に過ごしました。休日はホームステイ先でバディの家族と過ごし、一緒に登校して授業に参加します。18日(水)から3日間、Emmanuel Collegeの20名の生徒たちはバディの生徒との授業の他、桜美林幼稚園での交流や、剣道、書道などの授業に参加しました。最終日20日(金)の夕方にはfarewell ceremonyを行い、お互いに別れを惜しみつつひと時を過ごしました。

11月1日(金)から2週間の予定で、アメリカ合衆国ノースカロライナ州にあるSouth Academy of International Languages(S.A.I.L.)の生徒たちが来校しました。桜美林中高の生徒の家庭にホームステイをしながら、バディと一緒に登校、授業にも参加しました。

韓国の細花高校とは、2000年7月に正式に姉妹校協定を締結して以来、毎年両校の生徒が互いの学校を訪問する交流(桜美林は7月に訪韓、細花は1月に来日)を続けている。今年度は1月16日~20日の日程で桜美林中高を訪問、交流のため来日しました。桜美林中高の在校生宅にホームステイをおこなうため、学校での対面式を行ったのちにそれぞれのファミリーと対面し、一緒に家路へと向かいました。短い滞在期間でしたが、ステイ先の生徒たちの中には去年の7月にこちらから済州を訪問して交流を深めてきた生徒もいて、お互いに仲良くよい時間を過ごすことができたようです。また次年度以降の良き交流を約束しました。

10月21日(月)から24日(木)の日程で、韓国の姉妹校順天梅山女子高等学校が来日、本校の生徒たちとの交流が行われました。梅山高校の生徒たちは朝の高校1年生のチャペル礼拝から参加、午前中は書道の授業を体験、昨年12月に韓国の梅山高校を訪問交流した書道部の生徒たちがサポートをしました。午後は、中学生の音楽の授業に参加、中学2年生の合唱コンクール課題曲を共に合唱しました。その後、茶道部のティーセレモニーでお点前を体験し、放課後には中学校舎エントランスで国際交流委員会の企画による交流会でお互いの学校を紹介し合う時を過ごしました。交流会ではハンドベル部、ダンス部のの生徒たちによる演奏とダンスパフォーマンスが行われました。ほんのひと時の交流の時間でしたが、以前からの友人同士の親睦会のように大いに盛り上がり、お互いに素晴らしい時を共有できたようです。

来年度の活動計画
今年度はコロナも明け、学校行事や姉妹校交流のほとんどを再開することができた。コロナ過にオンラインの整備もなされ、授業スタイルや生徒間交流も多様かつ主体的になってきている。本校でも観点別評価を導入し、科目の授業のみならず、様々な課外活動も含めて、新しい評価方法を実施しつつあるので、そうした評価方法の実績を踏まえたカリキュラム全体の完成を目指していく。また、「探究・総合プログラムの中高6年実施」「新しい評価方法の導入」「DXハイスクールの採択」の内容を充実化させるとともに、上記の3つのプログラムを相互に連関させて、より発展した学びを進めていきたい。
