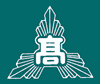
| 所在地 | 〒651-0054 兵庫県神戸市中央区野崎通1−1−1 |
|---|---|
| 電話番号 | 078-291-0771 |
| ホームページ | https://www.kobe-c.ed.jp/fki-hs |
| 加盟年 | 2007 |
2024年度活動報告
生物多様性, 海洋, 減災・防災, 気候変動, エネルギー, 環境, 文化多様性, 世界遺産・無形文化遺産・地域の文化財等, 国際理解, 平和, 人権, ジェンダー平等, 福祉, 持続可能な生産と消費, 健康, 食育, 貧困, グローバル・シチズンシップ教育(GCED)
ユネスコスクールガイドラインより、次の2点について重点的に取り組んだ。
1 持続発展教育(ESD)を通じて育てたい資質や能力を明確にし、自分で、あるいは他者と協働して、問題を見い出し、解決を図っていく学習の過程を重視した教育課程を編成するよう努める。
1-1 育てたい生徒の資質や能力の明確化
葺合高校で育てたい資質や能力を本校独自で定めた「Neo MAKS 12の力」とし、学校設定教科「国際」や「学際」の科目の中で、また総合的な探究の時間や学校行事の中で、連携しながらそれらの力を育成する。
Mind ① 物事を多面的に見る力 ② 他者の痛みを理解しサポートする力
③ 多様性の中で協働する力
Attitude ④ 経験と知識を融合させる力 ⑤ リーダーシップをとり責任を持って調整する力
⑥ 柔軟性に富んだ問題解決力
Knowledge ⑦ 自国や他国の文化・歴史に関する深い知識と理解 ⑧ 科学的知識を活用する力
Skills ⑨ ICTを主体的に使う力 ⑩ コミュニケーション力
Neo ⑪ 普遍的正義感 ⑫ 新しい価値観の創造
1-2 問題解決学習を重視した教育課程の構築
本校では、生徒が主体的にあるいは協働的に問題を見出し、解決を図っていく学習の過程を重視した教育課程を編成し、教科横断的な授業内容を展開した学際系の6科目を設定している。今年度も指導内容を精査し、指導方法の改善に努めた。
上記「Neo MAKS 12の力」をどの科目のどのような学習や実践活動で育てるかを決めている。
(1)グローバルスタディーズI(GSI) 国際科1年生 必修 ①⑥⑨⑩
(2)グローバルスタディーズⅡA(GSⅡA)国際科2年生 必修 ①④⑥⑨⑩
(3)グローバルスタディーズⅡB(GSⅡB)国際科2年生 選択 ①④⑤⑥⑩
(4)グローバルスタディーズⅢ(GSⅢ)国際科3年生 選択 ①⑥⑦⑨⑩⑫
(5)学際リサーチ 普通科2年生 英語系文系 選択 ①⑥⑦⑧⑨⑩⑪
(6)食生活実践 普通科3年生 文系選択 ①②⑦⑩
2 持続可能な開発のための教育を基盤とし、問題解決型科目と総合的な探究の時間、学校行事を連携させ、それぞれが生徒の学びを支えている。
2-1 社会に開かれた学びの実践――地域の社会教育機関、NPO等との連携
各学年の総合的な探究の時間での活動や国際・学際系科目の学びは、教室内にとどまることなく、社会に開かれた学びと実践の場となっている。今年度も国際機関、国内外大学、企業、自治体、NPO等の48講座を開催することができた。内容は、人権、ジェンダー平等、福祉、平和、持続可能な生産と消費、国際保健、防災、 グローバル社会、共生社会、コミュニケーションなどである。例えば、2年生国際科・英語コースの生徒はWHO Kobe センター所長による英語での”Global Health”に関する講義を受けた。また、希望者は、アメリカのスタンフォード大学のオンラインで授業を受け、「多文化共生」「平等社会」「起業家精神」「多様性」をテーマに、意見交換し、課題研究をまとめるStanford e-Kobe Programに参加した。
本校は年間2回、課題研究の発表・意見交換・解決に向けたディスカッションを校内・校外の高校生と共に行い、全校生徒が参加している。7月には、海外の姉妹校(スウェーデン・オーストラリア・インド・台湾・イラン?)が参加し、オンラインで高校生国際会議を運営し、課題解決のため活発な意見交換をした。1月には他の神戸市立高等学校や探究活動への取り組みが熱心な近隣の高校、市内のインターナショナルスクール等約10校を招き、様々な分野の発表に対して、日本語・英語でディスカッションを行った。
昨年度に引き続き、フィリピンのフィールドワーク・オーストラリアとの交換留学を行ったほか、スウェーデンから高校生を招き、日本の文化について議論を深めた。また、そのほかにも、来年度の国際理解教育をより充実したものとするため、新たに、台湾、アメリカ、オーストラリア、香港、フィリピンなどとの学校間交流の話し合いを進めている。これにより、世界の諸問題について話し合う機会を得ることができた。
来年度の活動計画
2025年度は、新たに4つの国際交流を企画している。海外の高校生と世界の諸問題について議論する機会を持ち、グローバルリーダーの育成に努めたい。そのためには、日々の授業で、教科教育の枠を超えたトピックの学習が必須である。学際的な学びを軸とした、ESD教育をさらに進めていきたい。
